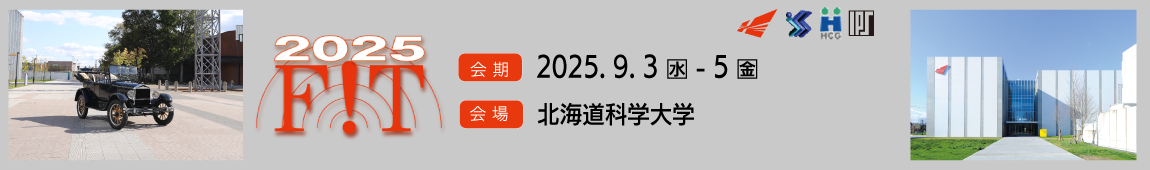イベント企画
将来の誤り訂正量子計算機と古典計算機の協調利用に関する研究
2025/9/5(金)9:30-12:00
第1イベント会場
第1イベント会場
| 【企画概要】量子計算機は,どんな問題でも現在の方式の計算機(古典計算機と呼ぶ)より高速に解けるわけでないので,量子計算機と古典計算機をうまく使い分けて,効率よく与えられた問題を解くという考え方が提唱されている.実際,量子計算機と古典計算機の協調利用の具体的な方法を考えようとすると,古典計算機の利用方法や量子計算のための量子回路設計手法などについて,明らかにしなければならない様々な問題がある.また,量子と古典のハイブリッドなアルゴリズムで有用なものを考えるという理論的な問題も存在する.本シンポジウムでは,量子計算機と古典計算機の協調利用を実現するために解決しなければならないいくつかの問題に関して,同分野で活躍する研究者により研究紹介を行う. | |
9:30-9:50 講演(1) 量子計算機と古典計算機の協調利用の枠組みの開発 | |
| 山下 茂(立命館大学 情報理工学部 教授) | |
| 【概要】量子計算機と古典計算機をうまく使い分けて,効率よく与えられた問題を解くという考え方が提唱されているものの,その具体的な方法はあまり議論されていない.量子計算機と古典計算機を単独で使用するよりも,協調して利用した方が効率よく計算できる状況として,問題を部分問題に分けてその部分問題を量子計算機と古典計算機のより適した方を用いて解くという枠組みを検討している.その枠組みを開発するために必要となる研究項目の紹介を行う. | |
 | 【略歴】1995年京都大学大学院修士課程修了.情報学博士(京大).日本電信電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究所・研究員,科学技術振興事業団今井量子計算機構プロジェクト研究員(兼務),奈良先端大・情報科学研究科・助教授を経て2009年より立命館大学教授.2020年 ミュンヘン工科大Global Visiting Professor,2012年国立情報学研究所・客員教授等.IEEE Transactions on CAD Best Paper Award,丸文学術賞,情報処理学会山下記念研究賞等受賞.情報処理学会フェロー. |
9:50-10:30 講演(2) 分散型計算における量子優位性 | |
| ルガル フランソワ(名古屋大学 多元数理科学研究科 教授) | |
| 【概要】本講演では、量子分散型計算(すなわち、ネットワーク上のプロセッサが量子メッセージを交換できるような計算モデル)に関する研究成果を報告する。分散型計算および量子計算の基礎について説明してから、量子分散型計算における量子的優位性を示す最近の成果を紹介する。また、量子分散型計算における興味深く重要な未解決問題についても述べる。 | |
 | 【略歴】2006年東京大学大学院情報理工学系研究科博士後期課程修了。2006年JST ERATO-SORST量子情報システムアーキテクチャ研究員。2009年東京大学大学院情報理工学系研究科特任講師。2012年東京大学大学院情報理工学系研究科特任准教授。2016年京都大学大学院情報学研究科特定准教授。2019年名古屋大学大学院多元数理科学研究科准教授、2022年教授。理論計算機科学、特に量子アルゴリズムの研究に従事。 |
10:40-11:20 講演(3) Qiskitを基盤とした高抽象内部DSL設計への試み | |
| 横山 哲郎(南山大学 理工学部 教授) | |
| 【概要】本発表では,量子アルゴリズムを抽象的かつ直感的に記述することを可能とする内部領域固有言語の設計と実装について述べる.提案する内部領域固有言語はPythonに埋め込む形で構築されており,Qiskitと高い親和性を保ちながら,論理演算・比較演算を自然な構文で表現することができる.自然な構文の表現には演算子オーバーロードを用い,記述された論理式を内部では構文木を中間表現として量子回路へと変換する.また,可逆性を担保するためにアンコンピュート処理を自動生成する仕組みを備える.本手法は,従来の文字列ベースの論理式の表現やAST変換型アプローチが抱える静的安全性・構文再利用性の制限を克服し,Qiskitの柔軟性を活かしつつ,記述性・抽象性・保守性を兼ね備えた量子回路構築環境の実現を目指すものである. | |
 | 【略歴】2006年東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了.2007年名古屋大学大学院情報科学研究科附属組込みシステム研究センター研究員.2009年南山大学情報理工学部ソフトウェア工学科講師.2011年同准教授.2014年南山大学理工学部ソフトウェア工学科准教授.ACM,日本ソフトウェア科学会,情報処理学会各会員.リバーシブルコンピューティングに興味を持つ. |
11:20-12:00 講演(4) 機械学習によるSAT求解時間の予測と量子・古典ハイブリッド計算への応用 | |
| 冨山 宏之(立命館大学 理工学部 教授) | |
| 【概要】充足可能性判定(SAT)問題は、計算複雑性理論における最初のNP完全問題として知られ、多くの応用を持つ重要な問題です。SATは、問題のインスタンスごとに求解時間が大きく異なることが知られており、本講演では、その求解時間を機械学習モデルにより予測する取り組みを紹介します。さらに、この予測を活用した量子・古典ハイブリッド計算への応用についても議論します。 | |
 | 【略歴】1999年九州大学・大学院システム情報科学研究科・博士課程後期課程修了。博士(工学)。カリフォルニア大学アーバイン校・客員研究員、九州システム情報技術研究所・研究員、名古屋大学・准教授などを経て、2010年より現職。 |